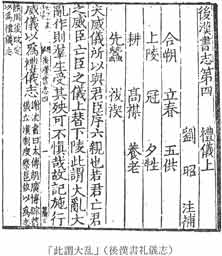
『邪馬一国への道標』 へ
『邪馬一国の証明』 倭国紀行 へ
古田武彦
古代史好きの方なら、時として目にしたことがおありでしょう。「倭国わこく大乱」という言葉。
一時よりいささか下火になったかに見える「邪馬台国」論議に代って、よく登場します。ことに古代史の“玄人衆くろうとしゅう”とも言える、考古学などの学者たちの文章の中でよくお目にかかるのです。ところが、その方たちの使用の仕方を見て、わたしは「ハテナ?」と首をかしげることがあります。文献の使用方法があまりにも無造作で、原典や史実から、意味がズレてしまったまま、全くそれに気づかずにいるのではないか。大変失礼ながら、わたしにはそう思われていたのです。しかも、このテーマを冷静におしつめてゆくと、その先にポーッと明るい曙光(しょこう)、つまり古代史の新しい局面が見えてくるのにわたしは出会ったのです。
しばらく、耳を傾けて下さい。
まず第一の問題、それは、「倭国大乱」という表現は、『三国志』の倭人伝にはない。この一点です。
「其の国、本(もと)亦男子を以(もつ)て王と為(な)し、住(とどま)ること七、八十年。倭国乱れ、相攻伐すること歴年。乃(すなわ)ち共に一女子を立てて王と為す。名づけて卑弥呼と曰(い)う」(三国志倭人伝)
この点を無造作に、あたかも『三国志』の原文にこの語句があるかのように扱っている論者があります。実は、「倭国大乱」とあるのは、『後漢書』倭伝です。『三国志』の倭人伝には右(上)のように「倭国乱」であって、「大乱」ではありません。
「桓(かん)・霊(れい)の間、大いに乱れ、更々(こもごも)相(あい)攻伐し、歴年主無し。一女子有り、名を卑弥呼と曰う。・・・是に於(おい)て共立して王と為す」(後漢書倭伝)
それなのに、口調がいいせいでしょうか、いつか「大乱」という表現の方が慣用されてしまったようです。もっとも、この点に関するわたしの指摘が紹介されてより(『「邪馬台国」はなかった』朝日新聞社刊)、「倭国乱」の形で引用する論者も時に現われてきたようですが、「乱らん」と「大乱」のちがいの“実質”には、まだ本当の目は向けられていないようです。“たかが「大きな」という形容句があるかないかだけじゃないか。目くじら立てるな”。まだそう感じでおられる方も多いはずですから。
わたしがこの問題に着目したのは、次の一節からでした。
「若し、君(きみ)、君の威を亡(うしな)い、臣、臣の儀を亡わば、上(かみ)替(すた)れ、下陵(しの)ぐ。此(こ)れを大乱と謂(い)う」(司馬彪、後漢書、礼儀志上)
つまり“臣下が君の威儀を犯す”。これが「大乱」だ、というのです。そしてこれをなさしめないことこそ「礼儀」の根本だ、というわけです。この礼儀志には「天子、三公、九卿、諸侯、百官」の行うべき儀式などが書かれています。つまりここで「君」というのは、当然、「天子」のことです。ですから、「大乱」というのは、下から“天子の位を犯す”ときに、はじめて用いられる。そういう、一種の大義名分上の述語なのです。
こう言えば、年輩の方々はあの戦前のことを御記憶でしょう。「大喪」「大礼」「大典」などと言えば、すべて“天皇に関する儀式”を指していました。民間の金持がいくら大枚(たいまい)をはたいて、豪勢な儀式を行ったとしても、それを「大喪」と言うわけにはいきません。いわば“大義名分のかかった”特殊用語なわけです。事実、この『後漢書』の礼儀志でも、この天子による「大喪」について、その儀式のあり方をのべています。
さて、この『後漢書』の礼儀志を書いたのは、司馬彪(ひょう)という人です。西晋(せいしん)の二代の天子恵帝の末年(三〇六)に死んでいますから、陳寿(ちんじゅ)と同時代の史家です(陳寿も、同じ恵帝の元康七年〈二九七〉に死)。けれども、彼は陳寿のような一介の史家、それも蜀(しょく)朝からの帰属者とちがって、名門です。西晋の帝室司馬氏の一員ですから、まさに“皇族”なわけです(司馬懿の弟の司馬進の孫に当る)。
司馬氏系図
(兄)懿ーー師ーー炎ーー衷〈次男〉(恵帝)
|
(弟)進ーー睦〈次男〉ーー彪
この点、陳寿とは、身分上、いわば“格”がちがう、といえましょう。その司馬彪の「大乱」の定畿。それは当然、同時代、同じ西晋朝の史官たる陳寿の使用方法と同じはずです。ことに、これはなおざりにできぬ、“大義名分上の用語”なのですから。
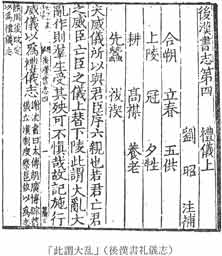
そこで『三国志』をしらべてみました。するとやはり、この本の夷蛮(いばん)伝にあたる烏桓(うがん)、鮮卑(せんぴ)、東夷伝(巻三十)には、全く「大乱」の語は出現していないのです。出現するのは、中国内部の場合ばかりです。たとえば、
「漢末、天下大乱、雄豪並び起る」(魏志、武帝紀)
のように。これは漢末に董卓(とうたく)、呂布(ろふ)などの豪傑が競いおこり、交々(こもごも)天子(献帝)の座をおびやかした非常事態を指す言葉ですから、まさに「天下大乱」にピタリです。その董卓伝にも、
「卓、既に精兵を率いて来り、適(たまたま)帝室の大乱に値(あ)い、廃立を専(もっぱ)らにするを得(う)」(魏志第六)
とあります。この「帝室大乱」という表現には、この用語の本来の意義が十分に現わされています。つまり一地方の一権力者内部の内輪もめや家督争いだったら、いくら争乱が領地全体にひろがり、かなり長期にわたったとしても、これは「大乱」と呼ぶにはふさわしくないのです。逆に、その争乱が“天子の座を犯す”という方向性をもっていたら、そのとき、はじめて「大乱」という名にふさわしいわけです。
このように考えてきますと、倭人伝中の倭国内の争乱は、いくらそれがその国の中では“大規模なもの”だったとしても、中国側から見れば、“コップの中の嵐(あらし)”です。決して中国の“天子の座を犯す”ていのものではありません。だから「大乱」とは書いていないのです。
この点、興味深いのは、同じ『三国志』中の、魏志韓伝の例です。
「部従事呉(ご)林、楽浪(らくろう)、本(もと)韓国を統ずるを以(もつ)て、辰(しん)韓八国を分割し、以て楽浪に与う。吏訳転じて異同有り。臣[巾責]沾韓(さくせんかん)、忿(いか)り、帯方郡の崎離(きり)宮を攻む。時に太守弓遵(きゅうじゅん)、楽浪太守劉茂(りゅうも)、兵を興して之を伐(う)つ。遵、戦死し、二郡遂に韓を滅す」
[巾責]沾韓の[巾責]は、JIS第3水準ユニコード5E58
中国側の出先官僚(部従事の呉林)の強圧的なやり方 ーーまさに現代的に言えば「大国主義」ですがーー が第一の原因。その上通訳上のふてぎわも重なって韓人側の憤激をまねいたのです。その結果、臣[巾責]沾韓の挙兵。これに応戦した帯方郡太守の弓遵まで戦死する、という大変な事態となりました。
韓国内の“コップの中の嵐”どころではない、中国側の現地支配機関の大ピンチをまねいたわけですが、ここでも陳寿は「大乱」という用語は使っていません。なぜなら、彼ら韓人は自己の土地の固有の領有権を主張しただけ。決して中国の天子の座に自分がとってかわろうとして起兵した、などという性格のものではないからです。
もっとも、帯方郡の太守は、当然中国の天子の任命による地方長官です。この点からすると、“その太守を殺したのは、とりもなおさず天子の権威を犯したものと見なす。つまり「大乱」だ”というような、一種の拡大論法がとれないわけではありません。事実、敗戦前の大日本帝国は、東アジア各地でこの種の手前勝手な拡大論法を乱用しつづけました。これはまだ東アジア各地に生き証人のたくさんいる、なまなましい歴史経験です。
しかし、三世紀の陳寿は後代の日本の官僚や軍人たちほど、狂熱的(ファナティック)ではなかったようです。決してこの事件を「大乱」視して叙述してはいません。もちろん、ここだけではなく、『三国志』中の夷蛮伝である、烏丸、鮮卑、東夷伝全体を通じて、「大乱」という表現は、全く、一回も使われていないのです。
以上によって、『三国志』の陳寿は、同時代三世紀の司馬彪の定義通り、「大乱」を大義名分上の特殊用語として使っていたことがハッキリしました。
ところが、これとは異った世界。それが五世紀、范曄(はんよう)の『後漢書』です。ここでは「大乱」の用法は、全くちがいます。
「章和元年(八七)鮮卑(せんぴ)、左地に入り、北匈奴(きようど)を撃ち、大いに之を破り、優留単干(ぜんう)を斬り、其の匈奴の皮を取りて還る。北庭大乱」(南匈奴列伝)
当時、匈奴は南北二つに分裂し、南は中国と和親政策を、北は独立政策をとり、各々「単干(ぜんう)」を立てていました。単干とは、“天の広大なさま”を意味するといいます(漢書、匈奴伝上)。要するに中国で言う「天子」です。その単干が鮮卑の侵入軍に斬られ、戦勝の証拠として皮を剥(は)いで持ち去られた、というのですから、北匈奴にとって未曾有(みぞう)の国難であったことは確かです。しかし、これはあくまで鮮卑対北匈奴の戦であって、中国としては直接関知せぬ話です。それどころか、中国に対して敵視政策をとりつづけ、中国の“目の上のたんこぶ”のような存在だったのが、この北匈奴ですから、この突発の変事は、中国にとってむしろ“歓迎”すべきこと。その逆ではありません。まして中国の天子の座をおびやかされる、ていのものでないことは、明白です。だのに、范曄はこれを「大乱」と呼んでいます(これを「大いに乱る」と読んでみても、それは日本式訓読の問題にすぎませんから、「大乱」という用語が存在すること自体、変りはありません)。つまり、五世紀の范曄は、この言葉を中国の天子中心の“大義名分の術語”としては使っていないのです。
ところでこの事件は、鮮卑、北匈奴たちの住む「北庭」では、明らかに大事変です。しかも北匈奴の「天子」に当る単干が斃(たお)されたのですから、これは「北庭における大乱」だ。こういう視点から、范曄はこの言葉を使っているのです。
こうしてみると、「三世紀の『三国志』→五世紀の『後漢書』」という変遷の中で、中国人の史眼が変化してきていることは、疑えません。つまり三世紀には、「全世界 ーーといっても、もちろん当時の東アジア世界が主体ですがーー の中心は唯一人。中国の天子だけだ」。これが、中国の官僚たちにとって疑いえぬ中心テーマでした。
ところが五世紀には変ってきたのです。“中国や匈奴や鮮卑など、各々の国々はそれぞれの「天下」をもっている”。こういう、いわば複眼的な視点になってきたのです。
もちろん、中国と鮮卑、中国と匈奴、それらが対等だというのではありません。根木的には“中国の天子の卓絶性”は、依然疑われているわけではありませんが、ともあれ、匈奴や鮮卑にも、各々独自の小宇宙があるという、その当然の事実を認めはじめているのです。
このようにのべてくると、皆さんの中には、“ああ、そうか。では、例の「臺(だい)の変遷」と同じなのだ”とうなずかれる方があるかもしれません。わたしの古代史の第二書『失われた九州王朝』を読まれた方ならご存じの、「三世紀の臺と五世紀の臺とは、使用法が一変した」という、あのテーマです。
わたしの今までの本を読んでおられない方のために、簡単に申しましょう。
『三国志』には、「・・・臺」の形が頻出(ひんしゅつ)します。たとえば「銅爵臺」「金虎臺」「陵雲臺」「南巡臺」「東巡臺」といったように。これらは魏(ぎ)の天子の宮殿です。かつては(漢代)単に“高地、宮殿”といった意味にすぎなかった、この「臺」の字。それが魏朝では“天子の宮殿”をしめす特殊の用法となってきたのです。その結果、「臺」一字で“天子の宮殿とその直属官庁”を意味するようになります。倭人伝にも出てくる「臺に詣(いた)る」といった類の用法がそれです(以上、『「邪馬台国」はなかった』参照)。
これに対し、四世紀以降はちがってきました。もっとも早くからある匈奴の単干臺をはじめ、羯(かつ)の霊風臺、羌(きょう)の留臺、といったふうにいわゆる五胡十六国、きそって交々「臺」を称したのです。いわば東アジアにおける「臺のインフレ」です。范曄の『後漢書』はそのような状勢をうけた五世紀の真っ只中(ただなか)に作られたのです。ですからこの本で「邪馬臺」という表現が夷蛮の国名の中に現われてきても、何の不思議もないのです(ただこれはあくまで「ヤマ臺ダイ」であって、「ヤマト」の表音表記ではありません。『失われた九州王朝』第一章II参照)。つまり、これは後漢代、一〜二世紀時点に対する表現ではありません。范曄の生きていた南朝劉宋代、つまり五世紀時点の表現なのです(後漢代に対する表記としては「倭奴国」「倭国」が表われています)。 ーー以上が「臺の変遷」問題です。これを一言で要約すれば、「臺の唯一特殊用法」の時代から、「臺の多元的使用」の時代へ、というわけです。
この問題が、先にのべた「大乱の変遷」というテーマと相応していることがおわかりと思います。“それは分った。だが、それだけのことじゃないか。時代によって当てる言葉が変っただけ。実体に変りはない。それをことごとしく言いたてているだけだ”。そうおっしゃる方も多いと思います。ですが、真の問題は、ここからはじまるのです。
さあ、新しいテーマにかえりましょう。
倭人伝中、ここの個所は、研究史上ながらく論議を呼んできました。第一、「住(とどま)ること七、八十年」という言い方が、何だかあいまいです。それに文脈上、一番の問題は、この一句が上にかかるか、下にかかるか、です。つまり王の即位期間が七、八十年なのか、それとも倭国が乱れたのが七、八十年なのか、どちらにとるか。まるで話がちがってきます。
前者にとると、一つの難点は“即位期間が長すぎる”ことです。全くありえないことはないにしても、生存期間としてもかなり長いこの年限が、即位期間とは。ちょっと気になる数値です。後者の方では、「住ること七、八十年、倭国乱る」という表現が漢文(中国文)としていささか不自然のようです。こういう場合、「倭国乱るること、七、八十年」という筆法が漢文としては、より普通ですから。
そこでこの「住」を「往」のまちがいだろうと考えて、「往七、八十年、倭国乱る」という論者が現われます(植村清二氏等)。これなら“過ぎし七、八十年間、倭国は乱れた”という意味になります。しかし“安易に原文を改定しない”という、わたしの立場から見ると、やはり“ハテナ”と首をかしげたくなります。
こういう場合、わたしの方法は単純です。『三国志』六十五巻全体のすべての同種の用法、それをしらべること、それしかありません。そこで調べてみました。「住」全十六個。すべて「トドマル」の意ですが、その中で“「住」プラス数字”の形をしめしているのは、次の一例です。
「登(とう 孫登そんとう。孫権の長子)昼夜兼行、頼郷(らいきょう)に到る。・・・(孫権への諫言かんげん)・・・住(とどま)ること十余日。西に還らしめんことを欲し、・・・」(呉志十四、孫登伝)
これは孫登(そんとう)が西の武昌から急いで父孫権のいる建業(今の南京)にやって来て、弟孫慮(そんりょ)の葬儀について父に諫言し、十余日の滞在ののち、もとの武昌へ帰って行った、というくだりです。 ここで「頼郷」といっているのは、老子の生まれた所として知られる河南省の地名ではありません。孫権のいた建業の西南に当る所です(盧弼ろひつ『三国志集解』孫休伝、永安三年項参照)。孫登はその頼郷に十日あまり滞在した、というのですが、ここで重要な点、それは「住る」という言葉がその前文の「頼郷に到る」という句を承(う)けて使われていることです。
このような筆法は何もここだけではありません。他の十五例も、同じです。
1 「卓(董卓とうたく)、独り衆を全うして還り、屯して扶風(地名)に住る」(魏志六)
2 「住る者は側席し、去る者は克己す」(魏志七)
3 〈魏志三十、倭人伝〉
4 「将軍と為(な)りて公安(地名)に住る」(蜀志十五)
5 「行旅皆住る」(呉志一)
6 「門に住ること、良(やや)久」(呉志七)
7 「以(もつ)て自ら安住せんと欲する耳(のみ)」(呉志七)
8 「潘璋(はんしょう 人名)、白帝(地名)に住る」(呉志九)
9 「寧(人名)乃(すなわ)ち夜往(ゆ)く。羽(人名)之を聞き、住りて渡らず」(呉志十)
10「備(人名)既に白帝に住る」(呉志十三)
11「軍住りて日を経(へ)、将吏之を患う」(呉志十四)
12「因(よ)りて新市(地名)に住り、拒を為(な)す」(呉志十五)
13「進みて江上に住る」(呉志十五)
14「百里(地名)の上(ほとり)に住る可(べ)し」(呉志十五)
15「立ちて道の側に住る」(呉志十九)
でも、「還る」や「進む」の類の動作をうけて、この「住る」が用いられているのです。これは「とどまる」という動詞が“ある動作の停滞”を意味することから見れば、あたりまえのこと、といえましょう。また、
「(士仁)将軍と為りて公安(地名)に住る」(蜀志十五)
という例では、「・・・(身分)と為る」という句を承けて使われているのが注目されます。こうしてみると、倭人伝中の問題の一節は、「王(身分)と為し」という、前句を承けて「住ること・・・」という句形につながっている。こう考えるほかありません。つまり“在位期間”です。これに対し、「倭国乱れ、相(あい)攻伐する」という状況の期間は、すぐその直後に書かれています。「・・・(する)こと歴年」の一句につながっているのです。
この「歴年」という言葉も、『三国志』中の慣用句の一つです。
「今兵興りて歴年」(呉志十三、陸遜りくそんの孫権への上疏じょうそ)
この「歴年」というのは、何年くらいでしょうか。呉の創建が黄武元年(二二二)で、この上疏の年が黄竜元年(二二九)ですから、この八年間内、ということになりましょう。
「(呂岱ろたい)初め交州に在ること歴年」(呉志十五)
呂岱は延康元年(二二〇)に交州の刺史(しし 郡国の督察官)となりましたが、黄武五年(二二六)には海東四郡を広州として、自らその刺史となっています。従って「初め・・・」と言っているのは、二二〇〜二二六年問の七年以内のことと思われます。こうしてみると、「歴年」とは、おおよそのところ“七、八年くらいの間”を漠然と指す用語のようです。
「遠年を歴(へ)て成功を致す所以(ゆえん)に非ざるなり」(呉志十二)
ここでは「歴二遠年一」とあります。これに比べると、ただの「歴年」の場合、そんなに長期間ではない。せいぜい“十年未満”というところではないでしょうか。とすると、「倭国乱れ、相攻伐した」のも、とても十年には満たぬ、数年間のこと、そう見るのが『三国志』全体の慣用的表記法のしめすところでしょう。
この“戦乱の歴年”のあと、卑弥呼が即位するのですが、彼女が中国側の視界に登場するのは、景初二年(二三八)の第一回の遣使によってです。そのとき、卑弥呼の即位からどのくらいの期間が経過していたのでしょう。それは正確には不明ですが、“それほど長い期間ではない”ように思われます。なぜなら、その即位のとき卑弥呼は「年已(すで)に長大」だった、とあります。その上、「即位→遣使」間がかなり長ければ、例の「遠年を歴(ふ)」といった類の記載があってしかるべきだからです。
“いや、それについては中国側は知らなかっただけだろう”。こういう考え方もありましょう。しかし、
(1) 戦乱期間 ーー (2) 「即位〜遣使」期間 ーー (3) 遣使
〈歴年〉 〈景初二年〉
![]()
とあって、(1)と(3)だけ書けて、「(2)だけが全く知識がない」というのも、変なものです。ゴタゴタ言いましたが、要するに、「何年かの戦乱のあと、卑弥呼が即位し、やがて(ほどなく)景初二年の第一回遣使となった」。そういう感じの文面なのです。
ところで、後漢の滅亡は建安二十五年(二二〇)。ここから魏代。卑弥呼の第一回遣使(二三八)の、ほぼ十九年前です。とすると倭国の“戦乱の歴年”は、この中にスッポリ入ってしまうこととなるでしょう。つまり、この「倭国乱れ相攻伐すること歴年」という事件は、後漢代ではなく、魏代内のことなのです。
以上のようにのべてきますと、読者のなかには次のように反問される方があるかもしれません。“しかし、その戦乱のことは、普通、学界では二世紀の後漢代のこととされているではないか。現に「桓かん・霊れいの間」とか、「漢の霊帝光和中」とか書いてある史書があるということだ”と。
その通りです。それは次の二文です。
(A) 「桓・霊の間、大いに乱れ、更々相攻伐し、歴年主無し。一女子有り、名を卑弥呼と曰う。・・・是に於(おい)て共立して王と為す」(後漢書倭伝)
(B) 「漢の霊帝光和中、倭国乱る。相攻伐すること歴年。乃(すなわ)ち共に一女子を立つ。卑弥呼、王為り」(梁書りょうしょ倭国伝)

『三国志』が「住七、八十年」とか「歴年」とか、一種あいまいな表現なのにひきかえ、こちらは絶対年代が明確です。ですから、「この絶対年代のどちらかが正しい」。そう思いこみたい誘惑が、従来の史家の頭をとらえてきたのは確かです。しかし、事の真相を冷静に見つめているうちに、そのような誘惑は、しょせん史実とは無関係なこと、それをわたしは疑えなくなってきたのです。
その根拠は、簡単な“謎(なぞ)解きパズル”です。皆さんも、あまり固苦しくなく、日曜の午後、週刊誌に付載された数字パズルを解くようなつもりで読んでみて下さい。まず、『後漢書』で言う「桓・霊の間」とは、いつのことでしょう。
桓帝 ーー 本初元年(一四六)〜永康元年(一六七)
霊帝 ーー 永康元年(一六七)〜中平六年(一八九)
ですから、“桓・霊の間”とは、「その両帝の全期間中」という意味なら、「一四六〜一八九」の約四十年間となります。これに対し、「桓帝の末期から霊帝の初めにかけてのころ」という意味なら、“一六七年前後”という意味になります。
これを前者のように解した場合もあるようですが、これは明らかに誤読です。なぜなら、この『後漢書』の文面をよく見つめて下さい。「倭国大乱の末期、倭国に『主』が何年かいなかった。それがおさまってやっと卑弥呼という女王が共立された」。そう書いてあるのです。
従って「倭国大乱」が霊帝の末の一八九年ころ終ったとしたら、卑弥呼が即位したのも、この頃になります。つまり卑弥呼第一回遣使までにすでに約五十年間(一八九 → 二三八)の在位期問を経過していたことになります。このあとも、卑弥呼は少なくとも、狗奴(こうぬ)国と交戦した正始八年(二四七)ころまでは在位していたことが確実ですから、在位は“通算六十年を越えた”こととなりましょう。これは即位のはじめ、すでに「年已(すで)に長大」(三国志)だったという卑弥呼としては、何としても異常です。
だからこれはやはり、後者の解釈が妥当だということになります。つまり“一六七年前後、倭国に「大乱」がぼっぱつし、それは卑弥呼が即位した景初二年(二三八)ころまでつづいた”という理解です。そして“その終りの何年か(歴年)は、「主」無き期間すらあった”というのです。ここでは「歴年主無し」と、「歴年」は「無主」期間とされているのに注意して下さい。“一六七年前後以来の長年月の「有主」戦乱期につづき、ついに二三八年直前の何年かは混乱の極、「無主」戦乱期となるに至った。そして新女王が登場したのだ”。これが范曄(はんよう)の描いた図式です。
ではその「有主」から「無主」にわたる混乱期は何年つづいたのでしょう。簡単な引き算です。
“238 −(マイナス) 167=71”
ところでこの一六七というのは、桓帝(かんてい)退位、霊帝即位の年です。この年からなら、「霊帝之初」と言えばよいわけで、“桓 ・霊の間”と両帝にかけて言う必要はありません。つまり、「大乱」ぼっぱつは、やや桓帝の晩年にくいこんだ頃からぼつぼつ始まっていなければなりません。とすると、この「71」という数字は「70〜80」くらいと修正すれば、ちょうどいいこととなります。
そこです。例の「住(とどま)ること七、八十年」という、『三国志』の数値。それがここにズバリ顔をみせてきたのです。
この奇妙な一致に気がついたのは、わたしがはじめてではありません。それどころか、研究史上の著名な一論点をなしてきたのです。
たとえば、菅政友(かんまさとも)は『三国志』の「住七、八十年」を“景初以前の七、八十年”と解し、『後漢書』はこれによって計算し、“桓・霊の間”という一句を造出した、そう考えたのです。逆に白鳥庫吉は『後漢書』のこの一句は魏志・魏略以外の“独立史料”によったもの、と考えました。こう考えると、逆にこの“独立史料”をもとに陳寿(ちんじゅ 三国志の著者)が「住七、八十年」の句を造作した、こう考える論者も出てくるわけです。
しかし、今はそのような研究史論議はやめにして、ストレートに事実を確認してゆきましょう。
『三国志』の「住七、八十年」の文面は、ここだけなら、一応は前文と結ぶか、後文と結ぶか、その二つが可能です。しかし、『三国志』全体の「住」の用法から見ると、“前文の男王即位記事と結ぶ”ものと理解するほかない。つまり「七、八十年」は即位期間です。これはすでに論証した通りです。従って「まず“桓・霊の間”の句があって、これに従って陳寿が戦乱期間を“住七、八十年”とする文面を作った」。このような理解が成立できぬことは確実です。とすると、真の事の成り行きは、前者となります。つまり、「范曄(はんよう)が『三国志』の文面を誤読して、計算を行い、“桓・霊の間”の一句を造出した」。 ーーこれが結論です。これは大変な結論です。さらに念を入れて確認してみましょう。
第一は、次の「本」の一語です。
「其の国、本亦 男子を以て王と為し、住こと七、八十年、倭国乱れ・・・」(倭人伝)
この「本(もと)亦(また)」の語が男王問題にだけかかり、「倭国乱」問題にかからぬことは当然です。ところが、倭人伝の冒頭には有名な次の一節があります。
「(倭人)旧(もと)百余国。漢の時朝見する者有り、今、使訳通ずる所三十国」
ここで魏晋時代が「今」と呼ばれているのに対し、漢代は「旧もと」と書かれています。また、
「夫余、本、玄菟(げんと)に属す。漢末、公孫度、海東に雄張し、外夷を威服す。夫余王、尉仇台、更(かわ)りて遼東に属す。・・・今、夫余の庫に玉壁有り」(三国志巻三十、魏志夫余伝)
右では“夫余は本(もと) 、玄菟郡に属していた。ところが漢末以来は遼東郡に属するようになった”というのですから、ここでも「本」は漢代のことを指しています。そして一方で漢末のあとの魏晋を指す「今」の用語がここにも出現しています。
このような「本」と「今」の対比は、次の一文に鮮明に現われています。
「涓奴(けんど)部、本(もと)、国主。今 は王為(た)らずと雖(いえど)も、適(たまたま)大人(たいじん)を統ず」(魏志巻三十高句麗伝)
以上の諸用例と語法のしめすように、明らかに、
(A)本亦男子を以て王と為し、住ること七、八十年。 ーー漢代
(B)(今)倭国乱れ、相(あい)攻伐すること歴年。 ーー魏晋代
という関係なのです。これを(B)まで、「本」(漢代)の意に解してきた(范曄)をふくむ従来の読法、それは大きな錯誤におちいっていたのです。
范曄がおちいっていた、このような錯覚をもっともよく示すもの、それは「歴年主無し」の一句です。『三国志』では、「倭国乱れ、相攻伐する」ことが「歴年」の内容でした。ところが、范曄は、“七、八十年間もズーッと倭国が乱れつづけた”ように解したために、「歴年」を別のもの、つまり「主無し」の期間として、あて直すこととなったのです。
『後漢書』では、倭伝の最初に、
「国、皆(みな)王を称し、世世(よよ)統(とう)を伝う。其の大倭王は、邪馬臺(やまたい)国に居(お)る」
としています。倭国の大中心たる「大倭王」が「主」です。その「主」の不在時代が卑弥呼の直前にあった、范曄はそういうのです。
ここにおいて、わたしたちは、知ることができます。“なぜ、范曄は「大乱」と表現したのか”を。
第一に、彼は二世紀半ばころから、三世紀の三十年代まで、戦乱が七、八十年問もの長期間つづいた、と考えたのです。これなら、応仁(おうにん)の乱など、比べ物にもならぬ、日本史上空前絶後の「大乱」です。
第二に、しかもその“長期戦乱”の最終期は、“大倭王不在”という最悪期を迎えた、というわけです。つまり、倭国という、いわばこの「東庭」の領域内では、“君、君の威を亡い、臣、臣の儀を亡う”状況となったのです。つまり『後漢書』で採用された「多元化された“大乱”の用法」にピッタリです。しかし、遺憾(いかん)ながら氾曄は先にのべたように、根本において、『三国志』の文脈自体を誤断していたのです。
ーーこれがバズルの第一の解です。
「しかし、范曄は中国人だ。その彼が漢文(中国文)の文脈を誤断した、などとは、日本人のお前がおこがましい」。そうおっしゃる方もありましょう。ところが、同じ中国人で、「住七、八十年」を“前文と結びつけて”読解した史家もあるのです。それは先の(B)の『梁りょう書』の例です。七世紀前半の唐の人ですが、彼の眼前にあった史書に、『三国志』と『後漢書』の二つもふくまれていたことは、確実です。
「安帝の永初元年(一〇七)、倭の国王帥升(すいしょう)等、生口(せいこう)百六十人を献じ、請見を願う」(後漢書、倭伝)
この「帥升」というのが、倭国史上に名前の登場した最初の「王」です。「女王」とは書かれていませんから、まず、「男王」と見ていいでしょう(この直前の建武中元二年〈五七〉の「倭奴国金印授与」の項については、王名など一切書かれていません)。これは漢代です。そこで『三国志』の「其の国、本(もと)亦(また)男子を以(もつ)て王と為(な)し」の「男王」を「この男王と同一人物だ」と推定したら、どうなるでしょうか。
(a)帥升の遣使 ーー 一〇七
(b)男王在位期間 ーー七、八十年
つまり、この男王(帥升)は、「一七七〜一八七年」頃まで在位したことになります。そしてその時点が「倭国の乱」の開始時期ということになります。これを中国の絶対年代で表現してみましょう。

問題の十年間は、「霊帝の光和年間」をスッポリ包みこんでいます。ところが、『梁書』では、右の一句がまさに「倭国乱る」の開始時点とされているのです。つまり、「住七、八十年」を在位期間と見なした上で、「後漢書の帥升=三国志の男王」という等号に立つとします。すると、ガタン、ピシャリと、計算機は、自動的に「霊帝の光和中」という、「倭国の乱」の開始時点をしめす一句をはじき出す。そういうしかけです。それこそまさに姚思廉(ようしれん)の計算方法だったのです。
ーーこれが第二のパズルの解です。
しかし、これに対して、次のように言う方もありましょう。「いや、逆だったかもしれない。姚思廉の記載した一句、“霊帝の光和中”の方が本来の漢代史料だった。それを見た西晋(せいしん)の陳寿(ちんじゅ)が同じ計算で、「住七、八十年」という数値をはじき出したのだ」と。確かに、
○帥升の遣使 ーー 一〇七
〇霊帝の光和中(倭国の乱の開始) ーー 一七八〜一八四
という二史料から、「住七、八十年」をはじき出すことは当然できます。先の計算とは足し算と引き算のちがいだけですから。では、事の真相はこのような経緯だった、こう考えてもいいのでしょうか。残念ながら“否!”です。なぜなら、次の史料を見て下さい。いずれも『三国志』です。
(A) 「殤(しょう)・安の間に至り、句麗王(くりおう)、宮(きゅう)、数(しばしば)遼東を冠(こう)す」(魏志、高句麗伝)
(B) 「順・桓の間、復(また)遼東を犯す」(魏志、高句麗伝)
(C) 「桓・霊の末、韓、彊(きよう)盛、郡県、制する能(あた)はず。民多く流れて韓国に入る」(魏志、韓伝)
(A)の“殤・安の間”は「殤帝(一〇五〜一〇六)と安帝(一〇六〜一二五)の間」のこと、(B)の“順・桓の間”は、“順帝(一二五〜一四四)と桓帝(一四六〜一六七)の間”のことです。この二帝の中に、冲帝(ちゅうてい 一四四〜一四五)と質帝(一四五〜一四六)の三年間がはさまれています。また(C)の“桓・霊の末”は、「桓帝と霊帝の末(一六七及び一八九)」です。
これは、いずれも東夷伝の例ですが、もちろん中国内部(本紀、列伝)にも、この種の句法(絶対年代のしめし方)は、ありふれています。そのような句法を慣例としている陳寿です。その彼が眼前の史料に“桓・霊の間”とか“漢の霊帝光和中”とかあるものを、わざわざあいまいな「住七、八十年」にひき直す。そんなことは意図不明。全くありえないことです。従って「陳寿が計算して書き直した」説は成り立ちません。やはり姚思廉の方が仮説を立て、計算し、この中国風年代表記に“作り変えた”のです。
姚思廉の試行と苦渋は、その文面中にハッキリとその痕跡(こんせき)を残しています。なぜなら、光和中(一七八〜一八四)に倭国の乱がぼっぱつし、それから「相(あい)攻伐すること歴年」、つまり、十年足らずのうちに卑弥呼が共立されるのですから、少なくとも一九四年前後には即位したことになりましょう。とすると、景初二年(二三八)の最初の遣使までにすでに四十四年たっていたことになります。即位時ですら、「年已(すで)に長大」のお婆さんがーー 。こんな矛盾がここでもふたたび露呈せざるをえないのです(この点、後に改正。卑弥呼の登場は四十代半ば。『邪馬一国の証明』一七〜二二頁参照 ーー倭国紀行 卑弥呼の年齢その一)。あちら立てれば、こちら立たず、范曄(はんよう)も、姚思廉も、現代の論者と同じく、早くから「邪馬台国」論争の迷路にまきこまれてしまっていたようです。
では、ここで話を本筋にとりもどし、ズバリ史実に向いましょう。『三国志』全体の表記法から倭人伝を見る限り、「倭国の乱」は、三世紀魏代の事件だった、こう見なすほかはありません。ですが、もう一つ、つめるべき問題が残っています。それは男王の真実(リアル)な在位期間です。
その「住七、八十年」という表現が、中国風絶対年代からの“翻訳”でないことは、すでにのべました。とすると、当然、“魏使が倭国で聞いた”ことになります。つまり“倭人の報告による史実”です。こう考えてくると、突然、一つのサーチライトの光が横合いから飛びこんできます。そう、『「邪馬台国」はなかった』を読まれた方なら、ご承知の「二倍年暦」の問題です。要約してみましょう。
「魏略に曰(いわ)く『其の俗、正歳四節を知らず。但々(ただただ)春耕、秋収を計りて年紀と為す』」
これは倭人が「春耕」「秋収」の二点において年紀(年のはじめ)をもっていることをしめした文です。この理解に立つと、倭人伝のつぎの記事のもつ謎(なぞ)も氷解します。
「その人、寿考(ながいき)、或は百年、或は八、九十年」
つまり平均年齢九十歳くらいだというのですが、これを「二倍年暦」と見なすと、その実は四十五歳くらい。弥生期の日本人の人骨のしめす実際の寿命とよく符合してくるのです。その上、『古事記』『日本書紀』のしめす天皇の平均年齢も九十一歳ですから、右の視点から見ると、ピタリ謎が解けるわけです。また、わたしが『「邪馬台国」はなかった』の最後で提起した裸国、黒歯国の問題。その「東南、船行一年」も、二倍年暦の視点から、実日程「船行半年」と見なしたとき、解けはじめること、すでにのべた通りです。さらに九州北岸の対岸たる朝鮮半島南端でも、この二倍年暦が用いられていた形跡のあることも、すでにのべました(『邪馬壹国の論理』朝日新聞社)。
このような視点から見れば、この「七、八十年」の在位期問も、実は「三十五〜四十年」の在位期間となるのです。これなら、長いとはいっても、“空想的だ”とは言えません。何しろ、現代でも、すでに「昭和」の天皇の在位期間は優に五十年を越えているのですから。
つまり、この男王は二世紀の八十年代(一八○〜一九〇)に即位し、後漢末(二二〇)前後まで在位したと思われます。この“長期安定政権”を支えた男王の没後、「倭国の乱」がはじまったのです。それは後漢が亡ぶ前後の頃ですから、有名な公孫氏(こうそんし)問題がからみます。
後漢末期、公孫氏は遼東にあって、楽浪(らくろう)郡を支配し、さらにその南半を割(さ)いて帯方(たいほう)郡とし、それをも支配していました。すなわち、右の倭国の男王は、公孫氏を通じて後漢朝に貢献していたはずです。この記事が中国側の史書に記載されていないのは、次の二つの理由による、と思われます。
第一に後漢代の同時代史書がないこと。范曄の『後漢書』は、五世紀の成立ですから、そのとき遺存していた史料だけは使ったものの、散佚(さんいつ)していた史料も多かったはずです(西歴三一六の西晋の滅亡による大損亡)。
第二に、後漢末期、漢の最後の天子は献帝(一八九〜二二〇)です。これがちょうど、右の倭国の男王の期間にほぼ当っています。この間は、中国ではまさに「漢末の大乱」の期間です。倭国との交渉どころではありません。従って中国側の正史に反映しないのも、無理はないのです。
以上によって、パズルはほぼ終局を迎えたようです。
最近、考古学者の間で盛んなものに、「高地性集落」についての論議があります。瀬戸内海から近畿に及ぶ、この特異な集落は、はなはだ興味深い問題です。
そのときしばしば引き合いに出されるのが、この「倭国大乱」です。そしてこれを「桓・霊の間」や「霊帝の光和中」という絶対軸の上において、そこから右の「高地性集落」の年代を考えたり、さらには倭国の規模を考えたりする。そういう論者も多いようです。
この「高地性集落」自体については、興味深い問題として改めて論じたいと思いますが、いま注目したいのは次の一点です。 ーー『後漢書』の「桓・霊の間」も、『梁書りょうしょ』の「霊帝の光和中」も、史実としては実体のない“まぼろしの絶対年代”だった、という一点です。なぜなら、それらは、范曄や姚思廉が、それぞれの文脈読解や仮説の上に立って計算し、その結果導き出された“試解”にすぎなかったのです。そしてそれは今までのべた通り、いずれもあやまっていました。
「まぼろしの倭国大乱」 ーーわたしは、だからそう呼んだのです。
『邪馬壹国の論理』 へ