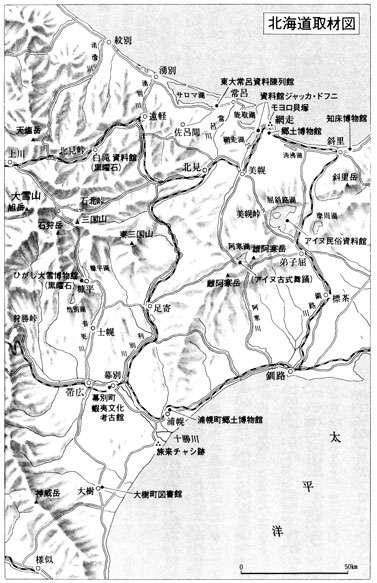
『真実の東北王朝』目次へ
古田武彦
巨大な夕陽だった。ビッグ・バン直後の宇宙のように燃えていた。燃えながら、地平の果ての森の上を、静かに左手から右手へと移動していた。 ーーここは、北海道。原野を突っ切るアウト・バーン、その一本道を、わたしたちの車は走りつづけていた。
人生で、いろんな風景に出会う。毎日のことだ。だが、生涯忘れられない光景に遭遇することがある。今が、それだった。
悠遠(ゆうえん)の古代からアイヌの人たちが愛しつづけてきた、その土地を、わたしたちは疾走(しっそう)していた。その人々なら、「神々の乗り物」と呼んだであろう、近代文明の申し子、ブルーバードに乗って、駆け抜けているのである。
「きれいですねえ」
「ええ」
運転している甲斐さんも、寡黙だった。お互いに、眼前の風景に心を奪われていたようだった。話すのが、惜しかった。このような光景を、記憶の手帳にきざみつけて、死んでゆける人間の生涯は、幸せだ。
今、「悠遠の古代」といった。アイヌの人々の祖先の時代のことだ。 ーーだが、それは“まちがいだ”、そういう見解を聞いてきたばかりだった。
浦幌(うらほろ)町の郷土博物館でお会いした後藤秀彦さん。この方にお会いできたのは、幸いだった。北海道で生れ、北海道で育ち、東京の大学で考古学を学んで、また北海道に帰った。北海道の空も海も土地も、皮膚から吸い込んで熟知している。そして「考古学」という、科学の目をもって、眼前の事物を認識した人。わたしにとっては、まさに、求めていた人だった。わたしの、しつこい質問に辟易せず、一つ一つ丁寧に教えて下さった。
わたしの幸運は、今というとき、各地の博物館、資料館で、そのような「生き字引」の方々にお会いできたことだった。大学を出、当館に勤めて、十数年。本当に、当地のベテランになった人々。各地の各博物館、各資料館で、そのような方々にお会いし、導かれたのである。後藤秀彦さんも、その一人。典型だった。
「アイヌ族の祖先ということで、辿れるのは、先ず、江戸時代までです。それ以前は、無理ですね」
「えっ」
わたしは驚いた。思いがけなかった。
「もし、百歩ゆずったとしても、八世紀まで。それ以上は、とても無理ですね」
しばらく沈黙したあと、わたしは口を開いた。
「この北海道の地名で、アイヌ語地名というのは、ずい分ありますねえ」
「ええ、ありますよ。この浦幌でも、札幌でも、そうでしょう」
「それ以外に、和語、つまり『北海道』みたいなのは別として、アイヌ語以外の言語でつけられた地名というのは、かなりありますか」
「さあ、そのへんのことは、わたしにはわかりませんねえ。そう、そう、井上寿先生あたりにお聞きになったら、どうですか」
さすが、後藤さん。こだわらずに、あっさりと、アイヌ語に精しい、当地の専門家の電話番号を教えて下さった。
帯広市内のホテルに着いて、夜、お電話した。同じ質問をした。
「さあ、そんなものはない、と思いますよ。大体、アイヌ語で解けると思います」
そこで、わたしは、さっき聞いた、後藤さんの説明をくりかえした。
「そうですねえ。考古学の方は、そう言っておられるようですが、それは、そちらの専門のことですから、わたしには、何とも言えません。ただ、地名については、今申したように考えています。アイヌ語以外の言語の地名が、古くから、かなりあったような形跡はありませんね」
筋目の通った、明快な説明だった。永年の蘊蓄(うんちく)をバックに、噛んで含めるような説明。説得力があった。
わたしは、ベッドで考えた。
もし、考古学の方で言っているように、現在のアイヌの祖先が、意外に新しい、つまり江戸時代以降か、せいぜい奈良時代以降だった、としたなら、必ずそれ以前は、「非アイヌ人の時代」だったこととなろう。旧石器・縄文等に当る時代にも、黒曜石をはじめ、古代文明の遺物は、数多く出現しているからである。
しかも、それは、江戸時代以降の何百年か、奈良時代以降の千何百年といった「短期間」でなく、何千年、何万年といった「長大な時間帯」のことだ。その時間帯の人々が、言語もなく、「地名」も必要としなかった、とは考えられない。
とすれば、もし、その人々が「非アイヌ人」だった、としたら、当然「非アイヌ語の地名」が存在したはずだ。とすれば、“新しく”奈良時代か平安時代にやってきた、“外来の”アイヌ人は、それら、以前の「非アイヌ語地名」をうけつぎつつ、新しい「アイヌ語地名」を付加していったこととなろう。ちょうど、現在の北海道の中に、「浦幌・札幌・室蘭」といったアイヌ語地名に対して、「北海道」「千歳」といった大和語地名が付加され、点在しているように。 ーーわたしは、そう考えた。
ところが、井上寿さんのお話では、そのような、「非アイヌ語地名」が残存しているような形跡はない、という。“アイヌ語では解けない”地名群の存在を見出せない、というのである。もちろん、網走などのオホーツク海沿岸に、ギリヤーク人が定住していたことは、有名だ。当然、「ギリヤーク語地名」の遺存の痕跡は存在するかもしれぬ。しかし、それは部分だ。例外だ。全体として、“北海道の地名は、アイヌ語で解ける”、この原則は変らない。
ーーこのような、井上寿さんの見解が正しい、としたら、「長大な時間帯」にわたる、「非アイヌ人の先在」というテーマは、これに対して「イエス」とはいいがたいのではないか。わたしの夜の思考は、そのように展開していった。
それでは、後藤さんからお聞きした「考古学上の常識」は、なぜか。 ーーわたしの思考はつづいた。
考古学者が「アイヌ人の器物」ないし「アイヌ人の生活遺跡」と見なすもの、つまり“判断の基準”とされているのは、当然ながら「二十世紀の、現代アイヌ人」のそれら(器具・生活方式)ではあるまいか。
それらとつながるものが、いつまで遡れるか。これが考古学者たちの「方法」だったのではあるまいか。その「方法」の帰結が、後藤さんのしめされた判断だったのであろう。
では、この「方法」を、わたしたち「和人」の場合にうつしかえて考えてみよう。たとえば、現代の東京、この二十世紀の東京人の使っている「器物」や「生活方式」の遡れるところ、それはどの時期までか。 ーーこういう「方法」をとった、とする。それで「日本人は、いつから関東地方にいたか」という問いに対する答を求めた、としよう。そうすれば、当然「明治以降」となるであろう。少し“甘く”しても、せいぜい「室町以降」といった形となるのではあるまいか。とても、「奈良時代以前から」とは、いくまい。それと同じだ。もしこれを、埼玉県や群馬県を「基点」にしてやってみても、大きく見て大差はないのではあるまいか。
要は、「現代の器物や生活方式がどこまで辿れるか」という問題と、「〜人がいつからいたか」という問題とは、同じではない。 ーーそういうことだ。
もう一つ、問題があった。
わたしの、今まで見た範囲では、アイヌの神話に「わたしたちは、他処(よそ)から来た」ことを語るテーマを見出すことができない。少なくとも、それが「メーンテーマ」になっている、そういう気配を見出したことがなかった。あの有名な「ユーカラ」や「アイヌ神謡集」といったものを見たところでは、そうだ。
もちろん、わたしにとって、まだ、それらに対する「知見」は、あまりにも貧しく、あまりにも乏しい。だから、それらを語る「神話」や「説話」に、将来お目にかかることがあるかもしれない。
たとえば、のちに沙流(さる)郡平取(びらとり)町の二風谷(にぶたに)の貝沢正さんや萱野(かやの)茂さんからお聞きしたような、
「オキクルミ・カムイは、ゆりかごに乗って、天上から、あの岩の上に降りてこられたといいます」
といった形の、「天からの降下」神話が、果して「天上」という名に“昇化”された、実は、他処(シベリア大陸など)の某所からの「渡来」をしめす「史実」の転化であった。 ーーそのような理解が果して成り立つのか否か、これも、今後、探究すべき「未知の謎」だ。
しかし、もしかりにそうだったとしても、それが「江戸時代渡来」とか、「奈良時代初期渡来」とかいった、そんな“新しい時代”の渡来をしめすものとは、到底わたしには、思えなかった。もし、そうなら、もっと生々(なまなま)しい形、たとえば「(シベリア大陸の)某地から、北海道の某地へ上陸した。そして先住民の某々を征服して定着した」というたぐいの、説話をともなっていたはず。わたしには、そう思われるのだ。
敗戦後、津田左右吉の「記・紀神話、造作説」が「定説」化し、“神話は史実に非ず”のイメージが研究思想となった。研究の基礎におかれたのである。そのため、学者たちは、神話のもつ、すばらしい史料価値に対して「鈍感」となった。率直にいわせてもらえば、そういうことだ。
だが、すでにしめしたように、それはちがっていた。たとえば、記・紀神話のハイライトたる「天孫降臨」の段、
「竺紫の日向の高千穂の久士布流多気( クシフルタケ)に天降りましき」
の一節は、真実な、しかも日本列島の歴史にとって、きわめて重大な史実を伝承し、記録していたのであった。
だとすれば、あの、アイヌ民族の伝承してきた、彪大な神話・説話群。日本人の教科書でこそ「無視」ないし「軽視」されているけれど、世界各地の研究者たちには、あまりにも著名な、「ユーカラ」をはじめとする、アイヌ民族の神話・伝説・説話大系。それらが彼等の、その土地に生きてきた、真実(リアル)な歴史と全く無関係であるとは、到底わたしには信じられない。それらは、わたしにとって、未知の、豊穣な、将来の探究のための一大宝庫なのである。
もちろん、その探究の帰結の指すところ、それは、わたしには、今は分からない。だから、未知の魅力を持つ。持つのだけれど、今のところ(もちろん、先入観となっては、いけないが)、
「ああ、アイヌ人は、他処から来たんだ。その証拠に、彼等の神話・伝説のメーンテーマが、そうじゃないか」
そういった形には、なっていない。そのように思われたのだった。
わたしが、アイヌ人にふれたのは、この旅行の終り近くだった。和田喜八郎さんが、
「いまアイヌたちが、内地から観光にくる人々にカムイの舞いを演じて見物させても、やがてそれも・・・」(『知られざる東日流(つがる)日下(ひのもと)王国』、八幡書店刊)
と書かれた通りの、「観光客向け」の新設家屋の中だった。阿寒湖のそば、湖畔の街並みの一隅である。だが、わたしは、そこで、アイヌ人の魂を知った。
かなり広い小舎、いや、会場だった。木造だが、がっしりしていて、アイヌの家屋を模したものであったかもしれぬ。が、大体は、芝居小屋のような印象だった。観光客が百人単位の団体で何団体か入っても坐れるように、座席数は多かった。前方に舞台があった。
そのときの観客は、わたしたち二人と、他に数人くらい。広い会場に、わずかの人数が散らばっていた。閑散としていた。
それでも、一日何回かの、スケジュールの定刻が来ると、はじまった。舞台に八〜九人の、アイヌの女性が登場した。民族衣裳をまとっていた。うんと若い、十代くらいの女性が二人。あとは、かなりの年輩の女性だった。その人々には、“入れ墨”ようのものが見うけられた。
次々と、アイヌの民謡が演ぜられた。背後に三名、老齢近い女性が「ムックリ」という竹の口琴で、曲を演奏した。それに合わせて、前面の六〜七名の女性が踊る。
山へ狩りをしに行く人々の歌、年寄りが子供たちに語る物語、そのいろり火をめぐる夜の歌、熊など、神から賜うた収穫を祝う祭りの歌など、など。くさぐさの、アイヌの生活のにおい、朝夕の光と影、それらがこちらへと、ハッキリ伝わってきた。
中でも、わたしの目と耳に焼きつけられた歌。それは、冬の長い夜、家の外で、ひっきりなしに風が吹き、草や木々がゆれている。ただそれだけを歌った曲だった。
前方の数人の女性たちが、「草や木々」になり、風に吹かれて、ゆらゆらとゆれる。しなう身体(からだ)と、長い黒髪をゆらし、ただそれだけで表現する。単調なリズム、吹きすさぶ風。それを「ムックリ」は、見事に表現していた。口にあてて吹くだけの、この単純な楽器は、まことにふさわしかった。身体を、髪を、あるいは軽く、あるいは強く、ゆらゆらと、ゆらせつづける女たちは、草や木々になり切っていた。 ーーそれらの音に耳を傾ける、家の中のアイヌの人々の生活、物おもい、歎きと喜び、その伝統と歴史、それが生き生きと伝わってきた。
わたしの中にこみあげるものがあった。わたしは、この人々を愛するようになってい。この大地に生きつづけてきた、アイヌの人々の思いが、わたしの心の壷に満たされてきたのである。
かつて、旧制高校生のとき、読んだ本があった。いや、読まされた、といった方がいいかもしれぬ。倉田百三の『愛と認識の出発』という本だった。
広島高校に入学して、二、一二日目。隣の席の男にさそわれた。「君、少し、話をしないか」 ーー「うん」と答えると、「どこか、空(あ)いた教室へ行こう」と、彼は言った。
注文通りの部屋を見つけた。向かい合(あ)って坐ると、彼は、言った。
「君、『愛、という問題について、どう思う。要するに、それをどう考えるかっていう、いわば『認識』の問題なんだけどね」
えらいことになった。十六歳の少年だったわたしは、内心、当惑した。なるほど、高校生になると、こんなことを議論しなければならないのか。相手がやたらに“年かさ”に見えたのである。
それから、何を話したか、おぼえていない。おぼえているのは、あとで、倉田百三の右の本を読んだとき、彼 ーー正木宏といったが口にしたテーマは、この本に“すじ書き”があったことだった。その本自体は、何やら“甘ったる”くて、あまり感心できなかった。あるいは、感心するほど、こちらが成熟していなかったのかもしれぬ。
ともあれ、わたしが今、青春の日の読書にまつわるひとときを、思い出したのは、他でもない。わたしたちが、ある対象を探究しようとするとき、その基本に、その対象への「愛」がもとになることは少なくない。ただ、それが“のめりこんで”しまうと、駄目。おそらく、いわゆる「愛の歌」でも、のめりこんでしまいっぱなしでは、作れないであろう。やはり、対象との「一定の距離」が必要だ。まして、学問の場合、主観的な「愛」と、客観的な「つきはなし」と、その二つの情熱の火がショートしあうところに、学問は誕生する。認識は前進する。
このようにして、わたしは「アイヌの大地」を、その心を、愛しはじめたようだった。
巨人に出会った。北海道、沙流(さる)川のほとり、二風谷(にぶたに)に住む、萱野(かやの)茂さんである。日高地方の平取(びらとり)町の中だ。
わたしと同年の方だが、アイヌ民族の生きた語り部である。
わたしは、萱野さんのお宅の玄関で、中から出て来られたこの方を見たとき、こう思った。
「人を見た」
と。今日(こんにち)、払底(ふってい)している「人」、人間ばかり、うじゃうじゃいる都会の街中を、日がな夕がな、探しまわっても、なかなか会えない「人」。その「人」に、ここ、北海道の沙流川のほとりで、ようやく会うことができたのである。
わたしはすでに、この人の名には“覚え”があった。東京の「古田武彦と古代史を研究する会」の、古くからの会員だった藤田誠三郎さんが、わたしにこの人の本を下さった。
『アイヌの碑』(朝日新聞社刊)
という本だった。
だが、久しく、わたしの本棚に“眠って”いた。ちょうど、あの『東日流外三郡誌』と同じように。「機」は、まだ熟していなかったのである。
このように思いかえしてみると、わたしが「自分ひとりの探究」と思いこんでいても、その実、多くの読者に支えられている、その事実に思い当る。
「古田の本には、この方面の話がない。その本を読ましてやろう」
そう、内心に思いついて、わたしにすすめてくださるのだ。だが、そのときは、わたし自身の関心が他に向かっていて、ふりむけない。ところが、ある日。 ーーこういう経過に、しばしば出会ったのである。
今、出会っている、この「人」には、わたしたちには“失われた”ものが、生きている。
わたしは“根なし草”のようだ。時々、そう思う。日本列島内の、どこが、わたしの故郷。そのように言える「土地」を失った、人間たちの一人なのである。
わたしの両親は、土佐人だ。父は、高知市。母は、安芸市。二人とも、家庭内の日常会話で、「ず」と「づ」を明晰に発音し分けていた。だから、わたしも、「耳」では、聞き分けられる。
だが、わたしは、父母の国、高知県で、住んだことがない。生れたのは、会津。喜多方(きたかた)市で生れた。ラーメンの名所になったのは、のちのこと、当時は、酒屋さんの白壁の目立つ、雪の深い町だった、という。「という」のは、わたしは、生後八ヶ月で、この地を去ったからである。旧制喜多方中学の英語の教師だった父は、広島へと赴任(ふにん)した。その汽車の中で、はじめて、おすしのお弁当の「米つぶ」を食べた、という。
少年時代は、広島県内を、呉(くれ)市・三次(みよし)市(十日市町)・府中市・広島市と、転々とした。いずれも、父の転任のせいだった。
大学は、仙台。卒業後、最初の教師生活は、信州松本。やがて神戸、京都と、日本列島を歩きまわった。あたかも、ジプシーのように。だから、この日本列島内に、「こここそ、わが故郷」と呼ぶべき、土地、をもたぬ。そのような、現代日本に“ありふれた”ジプシーの一人なのである。だからこそ、逆に、日本列島中、どこに住んでも、どこに死んでも、「そこが、わたしの故郷」、そのように思えるのかもしれぬ。
その点、この、「人」はちがった。北海道も、この日高地方、沙流川のほとりに生れ、ここで生きた。「アイヌこそわが民族」そのように誇り高く、いつも語り、いつも書いている人なのだった。
その著述は、左のように、多い。いずれも、アイヌを語る本だ。アイヌを愛し抜き、アイヌの中に生き抜いた本だ。これほど、自己の拠(よ)って立つ血と文明を背にし、その語り手と、ひたすらなりおおせるとは。わたしのような、各地域の「混血児」には、うらやましいかぎりだ。だから、このわたしと同年の「人」に会い、深く、深く、相契合したのであった。
遠慮なく言えば、この「人」こそ、日本列島の生んだ生きた“文化財”であろう。日本列島文明の、“無上の誇り”であろう。
この「人」、に、文化勲章を与えないでいるのは、要するに「選考者」の力量が足りないからにすぎぬ。
萱野茂氏著作目録
1 ウニペケレ集大成 〈菊池寛賞受賞〉 アルドウ刊
2 チセアカラ(アイヌ民家の復原、写真集) 未来社刊
3 おれの二風谷(随筆一五〇話) すずさわ書店刊
4 炎の馬(民話集) すずさわ書店刊
5 キツネのチャランケ(小学生日本の民話) 小峰書店刊
6 風の神とオキクルミ(絵本) 小峰書店刊
7 木ぼりのオオカミ(絵本) 小峰書店刊
8 オキクルミのぼうけん(絵本) 小峰書店刊
9 ものとこころ(資料館案内) 日本観光文化研究社
10 パスイは生き物 北都出版刊
11 アイヌの民具(作り方・図版・写真) すずさわ書店刊
12 写真集アイヌ(結婚式と熊送り) 国書刊行会刊
13 ひとつぶのサッチポロ(アイヌの昔話) 平凡社刊
14 アイヌの碑(自叙伝 )朝日新聞社刊
15 THE ROMANCE OF THE BEAR GOD(民話集)大修館書店刊
16 カムイユカラと昔話 小学館刊
17 たくさんの不思議 ーーアイヌネノアンアイヌーー (絵本)福音館書店
この「人」に、ノーベル文学賞やノーベル平和賞を与えないでいるのも、同じく、その「選考者」の目が、いまだ、この東アジアの東端に“とどいて”いないにすぎぬ。わたしは、本気でそう思う。人の知るように、ノーベル文学賞は「個人的作家」だけでなく、一つの民族を代表する「伝承的作家」にもまた、与えられている。それを一つのポイントとしているのだから。
「ノーベル平和賞」といったのは、他でもない。沙流川に、水力電気のダムを作り、「故郷の山村」が変貌させられてゆく、その「和人の暴挙」に怒り、年老いた貝沢正さんと共に、抵抗の炎をもやしつづけているのが、この「人」だからである。
“自民党”の日本政府も、“社会党”の北海道知事も、この「生きた巨人」の訴えの声に聞き入り、本気で答えようとしていない。
ジャーナリズムも、空しく、他(よそ)の国の「ダライ・ラマ」や「サハロフ博士」を賞揚するだけなのである。他の国のことを賞めそやしておけば、誰も、異論を言わないからだ。
ともあれ、わたしは、この「北の巨人」のしめす、民族の心の証言者としての、連続した仕事に対し、心の底からの敬意を送りたい。
わたしが北海道を目指した、一つの関心点、それは「環状土籬(どり)」の存在だった。千歳空港構築のさい発掘された、この様式の遺跡について、「認識」をえたかったからだ。
というのも、他でもない。東北地方の各地に分布するストーン・サークル、たとえば、秋田県鹿角(かづの)市大湯(おおゆ)の配石遺構。あれとの「相似」と「非相似」に注目したからであった。
「環状土籬」の場合、円形の、いわば「土製の垣根」に囲まれた、あるいは“区切られ”た、お墓である。何人(なんにん)か、埋葬されているのだ。
この点、いわゆるストーン・サークルも、同じだ。大湯に見られるように、二つの大きな円形に区切られた場所、その中に、石が各地点に集積されている。配石遺構だ。これが「お墓」か、「祭りの場」か、議論が対立していた、という。
ところが、配石遺構の下から「脂肪酸」が検出された。これは、“大型の動物の遺骸”が存在していた証拠だから、にわかに「お墓」説が有力になった、という。だが、まだ、すべての配石遺構の土から「脂肪酸」が見つかったわけではないから、断定はできない。そういう説明だった。
説明して下さったのは、鹿角市教育委員会の藤井安正さん。ここでも、永年、当地の考古学的出土物と取り組み、地道な努力をつづけておられるベテラン、その方にお会いできたのだった。
その御説明は、周到で、まことに筋が通っていた。けれど、わたしには、一つ、疑問が残った。
それは、「お墓」と「祭りの場」と、それは、そんなに“別物”か。 ーーそういう疑問だった。
たとえば、「お墓」だった、としよう。では、古代の人々は、ただそこへ「屍体」を投げこんだだけか。「屍体」という“物捨て場”だったのか。そんなことはない。整然たる配石の位置関係が明白に語っているように、明らかにこれは、“丁寧に構築された”そのあとかた。わたしたちが見ているのは、その「残映」なのである。
当然、彼等は、最大の敬意をもって、その遺体を、その人を“祭った”のだ。「お墓」は、すなわち「祭りの場」なのである。
逆もまた、真だ。「祭りの場」に、彼等は“ある人々”の遺体を葬った。“ある人々”とは、その当時、たとえば、大湯なら、縄文後期後半の時代だが、そのときのリーダー格の人々、あるいは「尊貴なる家族」であろう。
というのは、当時の人々が「全部」、ここに葬られた、と考えるには、“数や場所の広さ”が足りない。わたしには、そのように思われた。もし、「全部」がここに葬られたのなら、もっと「脂肪酸だらけ」の痕跡がなければならぬ。不謹慎な言い方だが、わたしには、そう思われた。
縄文を「平等社会」と考えたのは、もはや過去の「幻想」である。たとえば、栃木県宇都宮市の聖山公園跡の根古屋遺跡。縄文前期中葉の遺跡だけれど、ここには、「墓地」の“仕切り”があった。A群の墓地には、副葬品が「[王夬]状耳飾り」だけ。B群の墓地からは、副葬品が「管玉類」だけ。C群の墓地からは、副葬品が「石さじ」だけ。少しはなれた、D群の墓地には、副葬品は一切「なし」。明らかに、この社会が「身分差」ないし「階級差」をもつ社会であったことを、見事に「展示」して見せてくれていたのだ。
[王夬]状(けつじょう)の[王夬](けつ)は、王編に夬。JIS第三水準、ユニコード73A6
わたしがかつて、「縄文奴隷」の存在する可能性を予告したとき、それはわたしにとって、身のひきしまる「学問的冒険」だった。わたしが縄文社会にふれて、感じとったところ、考えたところ、その帰結が、それだった(『古代は輝いていた』第二巻、朝日新聞社刊。朝日文庫)。
しかし、今はもう、「常識」となった。国学院大学の小林達雄さんが説いておられるように、かつては「縄文時代の美(うる)わしい姿」と、絶賛された“母が子供を抱いて、共に遺骸となった”出土状態、それが実は、“奴隷(子育てのための乳母か)が、子供と共に葬られた姿”だったことが判明した、というのである。
海外から輸入されたマルクス思想、その歴史観の中の「原始共同体」の時代を、日本の「縄文時代」に当てはめようとした人々、その考古学者、古代史学者たちを“嘲笑(わら)う”ことは許されない。それは、「舶来思想」を咀嚼(そしゃく)しようとした、涙ぐましい努力の一里塚だったからである。
だが、逆に、それを「固定のテーマ」とし、それを疑うことを「許さじ」とする時代は去った。人間社会の中に「身分」があり、「階級」があり、「リーダー」があった、という点、「縄文」と「弥生」との間の「時代の壁」はすでに、とりはらわれたのだ。聞こうとしない人には、その「壁」のとりこわされる音がなお聞こえていないだけなのである。
さて、もとへもどろう。
今のべたように、ストーン・サークルは、「お墓」だった。また同時に、あるいは“それ以上”に、「お祭りの場」だった。なぜ、「それ以上」かというと、“その人の死”は一回だけだけれど、「お祭り」は、季節や歳月によって、くりかえし行われるからだ。
今でも、「四十九日」とか「七ヶ年」とか、「区切り」をつけて、親族が寄り集る。「名」は、死者へのお祭りながら、実は、その「名」に寄せて、人々が寄り合う。おのおのの身内の消息を語り合うのである。いわば、集会の場をもつ「名分」なのだ。
古代も、その点、変りはない。いや、それ以上に、そうだったのではないか。何しろ、電話もない、手紙・葉書といった郵便物もない時代だったのだから。当然ながら、「環状土籬」や「配石遺構」は、古代集会の場だったのである。
「問いかけの仕方」が大事。いつも、わたしはそう思ってきた。
あの、「神籠石」のときも、そうだった。「祭祀遺跡か、山城か」、久しく、その論争がつづいていた。それを「解決」したのが、佐賀県による「おつぼやま」等の神籠石群の発掘調査だった。このときも、今回の「吉野ヶ里遺跡」同様、見事な“金のかけ方”、“力の入れ方”がしめされた。肥前の人々は、いざ、というとき、キッパリと力を入れる、そういう伝統をもっているようである。
鏡山猛さんを団長とする調査団の発掘・研究によって、「判明」した。「山城」だったのである。これら、神籠石群のそばに、二重の柵列の延々と配置されていた事実が明らかにされたのだ。この調査報告のもつ意義は、大きい。筑紫、肥前、周防(すおう)と連なった、一大山城群、これは、「誰が」「誰を」「誰から」守るために造ったのか。この問題だ。もし、「大和朝廷」が、これを造らしめた、とするなら、なぜ、『古事記』『日本書紀』に、これに関する記載が絶無なのか。この問題だ。彪大な年月と彪大な人民を動員した、一大土木事業、ときは六〜七世紀である。
この問題だ。この問題を、「四世紀以降、あるいは五世紀以降、あるいは六世紀以降は(こんな言い方自体が「可笑(おか)しい」が)、近畿天皇家の統一支配の時代だった」という、天皇一元史観から解けるか否か。すべての古代史学、考古学者たちは、この問題から“目をそむけ”てきたのである。
それは、ともあれ、今の問題はこうだ。
「山城である、と決定したごとで、『祭祀遺跡』でなかったことになったのか」
これだ。福岡県の女山(ぞやま)の神籠石群の内側から、中広銅矛が三本、出土している点から見ても、弥生時代、何等かの活動の行われていた痕跡は十分。いわゆる祭祀遺跡であったとしても、不思議はない。要は、かつて「祭祀遺跡」であったところを中心にして、のちに「山城」が築かれる。そういうケースが(少なからず)存在することは、むしろ当然なのだ。
だから、この場合も、「祭祀遺跡か、山城か」という設問は、(もちろん、その形で行われた論争の意義は認めるけれども)いささか、「問いかけ」自体が“性急”だったのである(この点、松本清張氏も、同類の疑問を投げておられる)。
他にも、
「銅鐸は、祭器か楽器か」
「日本人はどこから来たか」
といった設問にも、「問いかけ」自体に、同様の問題があった。吉野ヶ里遺跡のさい、言われた
「渡来型と在来型」
といった分析にも、同様の問題がある。「問いかけ」自体、分類につけられた「名称」自体について、吟味し直すこと、それが真に学問的認識の出発、その基礎固めのために、肝要ではなかろうか。
わたしが、大湯のストーン・サークルに関心をもったのは、その位置だった。
海のそばでもない、川のそばでもない。太平洋岸と日本海岸との中間に当る山地、こんなところになぜ、巨大な、代表的な配石遺構があるのか。この疑問だ。
これに対して、わたしに「仮説」が生れた。そばにある「十和田湖」が、その秘密の鍵をにぎっているのではないか。そう思った。
この位置にある、この湖、これは“火山爆発”にまつわって生起した湖、つまり「火口湖」ではないか。
とすると、その「火山爆発」、あるいは“火を吐きつづける火山”に対して、この配石遺構が形成されたのではないか。そう考えた。
もう一つのヒントがあった。「クラ」だ。地図で見ると、この十和田湖の中に半島が突き出ている。そこに「御倉(おぐら)山」という山名が記されている。
わたしには、当時、この「クラ」という地名が興味の対象となっていた。
その経緯は、こうだ。佐賀県の腰岳へ行った。永年の課題を果したのである。昭和六十二年の十月二十三日。
ここは、黒曜石の山。九州随一の産地だ。北海道の十勝地方。信州の和田峠。出雲の隠岐島。国東半島沖の姫島。そして九州では、何といっても、質・量ともに豊富なのが、この腰岳だった。
この山のことには、何度か“ふれた”ことがあった。わたしの本の中でだ。この黒曜石の鏃(やじり)などの分布は、のちの、弥生時代の銅矛(どうほこ)・銅剣・銅戈(どうか)など、金属器の分布と“重なって”いる。だから、弥生の北部九州(卑弥呼の「倭国」の中心の場所、そして時代に当たる)を考える上では、必ずその背景として、この「縄文の腰岳文明圏」を考えねばならぬ。
そう思っていた。しかし、まだ、その山に登ったことがなかった。そこで、博多へ行ったおり、一日を空けて、この山をめざしたのであった。
ここでも、好意があった。博多で、邪馬台国研究会や九州王朝文化の会をやっておられる橋田薫さんの御紹介で、唐津の藤井悟さんが車でお連れいただくこととなった。郵政省関係のOB。御夫婦で、愛車を駆って、連れていって下さった。
すでに、お宅で、腰岳(こしだけ)の黒曜石を採取したものを、お見せいただいた。その上、それらを採取した腰岳の中腹へ案内して下さったのである。雨の中だったので、トラピストの修道院のあるという、項上近くへは行かず、そのバス道で探したのだけれど、そこでも、次々と見つかった。山全体の埋蔵量は、さぞかし、と思った(平成元年の夏、宿願を達し、項上部のトラピスト修道院へ行き、竹村太嘉子さんから、立派な黒曜石をいただいた。修道院建設当時のものだ。当時、畑を耕すとき、黒曜石の破片に悩まされた、という。このさいは、博多の灰塚照明さん、鬼塚敬二郎さん、柴田洋子さん、柴田文子さんたちと一緒だった)。
さて、その、帰途。伊万里の市役所に寄った。腰岳関係の資料をいただくためだ。教育委員会の社会教育課で、快く、種々のパンフレット類をいただいた。そのとき、わたしは問うた。
「こちらでは、黒曜石のことを何と言いますか」
いつもの問いだった。黒曜石の産地での問いだ。しかし、たいてい、その答えは決まっていた。、判りません」だった。時には、「やはり、黒曜石といいますが」といった答えもあった。しかし、わたしの欲しいのは「和名」だった。中国名ではなかったのである。今回も、無駄を覚悟して、聞いた。ところが、
「からすんまくら、といいます」
明快な、お答えだった。そこで発行されている広報には、同名が冠せられていた。
「それは、どういう意味ですか」
わたしがそう問うと、
「おい、みんな、知っちょるか、『からすんまくら』の意味ば」
と、課内にとどろく声で、“叫んで”見まわされた。九州人らしく、豪快だった。だが、みんな首を横に振った。
唐津へ向かう帰途、車の中で、わたしは話した。
「『からす』は、やはり、鳥でしょう。黒いですからね。『くら』は、祭りの場をしめす言葉です。『高御座(たかみくら)』の『くら』ですね。千葉県で、国立歴史・民族学博物館のある『佐倉』、佐倉宗五郎の『佐倉』も、“狭い倉”と書いて、祭りの場をしめした地名でしょう。それに、北アルプスの乗鞍(のりくら)岳も、『祝(の)り倉』つまり、『祝詞(のりと)』を申しのべた、祭りの場だったんではないでしょうか。あの『倉』です」
藤井悟さんは、「なるほど」と言っておられた。運転中だった。
これは“こわい”話だった。なぜなら、この「からすんまくら」という言葉は、当の黒曜石が「祭りの場」で使われていた時代、つまり、縄文時代に、すでに成立していた、そういう可能性をしめすからである。まさか、弥生以降、金属器の時代、すでに黒曜石の価値が一挙に下落したあと、こうした言葉がはじめて生れる、などとは、考えがたいではないか。
このような“こわい”テーマはさておき、この「くら」には、さらに後日、いや、継続譚があった。
博多の懇談会で、この話をしたところ、近畿にも、注目すべき「くら」のあることをお知らせいただいた。もと、近畿におられて、最近博多へ来られた方だった。「暗(くらがり)峠」だ。この「くら」も、そうではないか、と言われるのだ。
そこで、大阪の講演会(市民の古代研究会主催)の前日、そこへ行った。藤田友治さんの運転で、広野千代子さん、三木カヨ子さんも御一緒だった。
暗峠は、奈良県と大阪府の境をなす稜線にあった。そこにさしかかると、すぐ判明した。山全体に、しめなわを張ってある。少しはなれて、鳥居がその山に向かっていた。両者の中間がブッツリ削り取られていた。採石業者あるいは、採砂業者の「作業」である。だが、両側が残されていた。それで、この暗峠の地帯が、神体山に対する祭りの場であったこと、それが一目で判明したのだ。やはり、現場は踏むべきもの、それが痛感された。
このときの副産物。この地帯の展望場に立つと、大阪湾が東から西まで一望で見下ろせた。大阪湾に入ってくる船が一つ、一つ数えられるような感じ、まさに絶景だった。眼下は、日下(くさか)。あの、神武たちが目指した場所だ。蓼津変電所のあるところである。
わたしは、瞬時に、了解した。神武たちが、なぜ、この日下の地を目指したのか。問題は、この暗峠をふくむ稜線だ。ここをおさえれば、大阪湾岸全体を手中にできる。背後には、奈良盆地の南端部がひろがっている。同時に、奈良盆地まで侵入すべき端緒をにぎりうるのである。これも、現地に来れば一目瞭然。そういう感じだった。
右のような探究経験をもっていたから、ここ十和田湖の中に突き出た「御倉山」に注目したのだった。
大湯のストーン・サークルには、厚く火山灰がおおっていた。そこで、わたしは、十和田湖の火山爆発との関係を、藤井安正さんにお聞きしてみたのだけれど、否定的だった。
「十和田湖は遠すぎますからね」
これが理由だった。だが、ここには逆に、“現地にいる方の盲点”があるのではないか、そう思った。ここ、大湯のストーン・サークルから十和田湖まで、車で二十分。バスで三十分近く。遠い、といえば、遠いのだ。特に、現代人がこの間を歩く、とすれば、悲鳴をあげるかもしれぬ。しかし、縄文人にとって、そんなに“たいした距離”だったのだろうか、火山の噴き上げる「聖地」、否、「聖山」を目指して。わたしは、そう思ったのである。
その夜、十和田湖のほとりのさざ波山荘に泊った。ひとり、だった。わたしにとって、自分の「仮説検証」のための、単独の旅だったのである。
さざ波山荘は、ちょうど御倉山の真向かいにあった。静かで、忘れがたい民宿だった。
わたしにとって、恵まれていたこと。それは、十和田科学博物館の存在だった。年間、常時開放されている。その内実は、火山資料館といっていいくらい、火山学の科学的データがいっぱい、つまっていた。最初の火山爆発。十和田湖という火口湖の形成期。第二〜三次、さらに数次の爆発の中で、十和田湖の中に、また湾入部や半島が形成されていった過程。そして最後に、御倉山の半島部の中に、さらに火山爆発の行われた時期の様子も、ありありと記録されていた。模型図も、工夫して、いろいろと作られていた。
それらを見て、わたしに判ったこと、それは、大湯のストーン・サークルの形成された、縄文後期後半、十和田湖の真ん中から、さらに火が噴き上げていたことだった。大湯のストーン・サークル人たちが、これに無関心でありえたはずはない。夜も、煌々(こうこう)と、その噴煙の吹き上げる姿を仰ぎ見たことであろうから。
今でも、十和田湖の神秘は深い。わたしは、さざ波山荘の側から、御倉山の半島部を望み見て、夕の深いもやの中で、朝の輝く太陽の光のもとで、それを痛いほど、感じた。しかし、縄文時代は、それどころではなかった。この青く、深い湖面から、輝く炎が燃え上がっていたのだ。その光景は、想像を絶する。古代人がこれを、「神の仕業」と考えたとして、何の不思議があろう。そう考えない方が、不思議だ。
そして、わたしの、その思いを決定的にしたのは、数次の爆発時の火山灰が、その都度散乱し、落下した、その分布図を見たときだった。作製には、大変な苦労をされたことであろう。何枚も、何枚も、並列して展示された、どの分布図を見ても、それが広範囲にわたっているにもかかわらず、例の大湯のストーン・サークルの地域に“かかって”いないのである。
わたしが昨日見てきた、大湯のストーン・サークルに堆積した火山灰。それは、ずっと新しい、いわば「最近」のものだった。旧石器から縄文時代に当る時期、何回もの爆発があったけれど、それは、大湯のストーン・サークルの地域を“避けて”いるのである。
もちろん、これは偶然。というより、地球の自転や風の向きによる、いわば「必然」の力だった。だが、このような事実は、当然、縄文人には、熟知されていた。そこで、十和田湖に近く、「天から降りそそぐ災害」の及ばない、この大湯の地に、巨大な祭祀の場、火の神・湖の神を祭る場をもうけたのではあるまいか。 ーーわたしには、そう思われた。
と、考えると、この「大湯のストーン・サークル」は、大湯に住む人たちだけのためのものではなかったのではないか。火の神・湖の神を祭る尊貴なる一族がそこに眠り、死してもなお、その「祈り」をつづけていた、古代東北地方北辺の人々のために。そう信ぜられていたのではないか。
大湯と、少しはなれたところにも、配石遺構が発見されている。いずれも、巨視的に見れば、十和田湖に「近い」のだ。だから、十和田湖と、その湖を形造った火山、今も火を噴(ふ)きつづけていた火山、これを抜きにして、これら「十和田湖周辺のストーン・サークル群」を語れないのではないか。わたしはそう思いつつ、夜の眠りについた。
意外なことがあった。大湯の資料館でいただいた資料の中に、秋田県における配石遺構の分布図があった。それを見ると、古い時代のものほど、南側にあり、段々北上して、この大湯に至る。そういった傾向がしめされていた。いいかえると、縄文後期後半では、北部が中心だが、前期はむしろ、南部。そういった感じなのである。
わたしは、関西にいた頃から、この大湯のストーン・サークルには関心をもっていた。「北方の神秘なる遺跡」、そういった印象だった。だから、「古いほど、南寄り」という分布図には、いささか、頭脳の混乱を覚えたのである。山形県の分布図は、まだ作製されていないようだったが、福島県も、むしろ、大湯より“古い”方に属するようだった。
この「意外」が解決したのは、静岡県富士宮市の千居(せんご)遺跡に立ったときだった。
創価学会で有名な大石寺。その奥にある。直接、その寺域内ではないけれど、大石寺側で“買い取った”領域のようである。寺内で鍵をいただいて、ずいぶん歩いた。迷いながら歩いた。わたしは「方向音痴」だけれど、御一緒の山本和子さん、その友人のわたしの妻、その女性たちの直感に助けられて、無事到着した。囲いがあり、戸口に鍵がかかっていた。内部は広かった。
配石遺構は、報告書(小野真一編、加藤学園考古学研究所)どおり、その姿を残していた。活動的な山本さんが、「あ、ここにも」「ここにも、残っていますよ」と、飛び廻って次々と“見つけ”て下さったのが、印象的だった。
そこから見た、富士山。“はじめて”見た富士山だった。いつも見る富士山は、東海道や新幹線の方から。あるいは、山梨県側からだった。いつも、すばらしいとは思っていたけれど、これほどではなかった。はるか、かなたにあったものが、今は眼前にある。もちろん、大石寺の入口あたりからでも、十分「近い」けれど、ここは一層。しかも、寺院や記念館や商店や駐車場といった、「後代の人工物」のない、ここから見る富士山のすばらしさ。ここに配石遺構を作った古代人、縄文人の心が痛いほどわかった。一切の解説がいらなかった。
しかも、二十世紀の今とちがい、当時は燃えていた。何が。もちろん、富士山が。わたしは、いつも思っている。旧石器・縄文時代の日本列島、ことに東日本、ことに中部・関東地方を語るとき、必ず心に銘じなければならぬ一節がある、と。それは、
「富士山が燃えていた」
この一語だ。北斎の描いた「富嶽三十六景」、それは名作だ。広重の「東海道五十三次」中のもの、また梅原龍三郎の連作もある。だが、それらは、いずれも「死せる富士山」だ。休眠中の富士山だ。
だが、旧石器・縄文時代はちがった。朝の光に、夕のもやに、そして夜の闇の中で、燃え上がっていた富士山なのだ。それがいかなる姿だったか。「絶景」などという、あやしげな言葉の及びもつかぬ姿。彼等は、日常、その前で、その下で、生活していたのだ。
ここ、千居の地に、配石遺構を作り、富士山に相対し、祈りと祭りと魂を捧げた遺跡、それがこの千居遺跡だったのである。縄文中期末から後期前半期だ。
これに遡るのが、長野県大町の上原(わっぱら)遺跡。縄文前期中頃から末期にかけてだ。
そして何よりも、あの阿久遺跡。八ヶ岳山麓の縄文都市。それは、縄文前期前半だ。次いで、縄文前期後半、そこには広大な、楕円形の配石遺構があった。何万個もの石が並べられ、中央部には、同じく楕円形の空地部分(配石のない部分)があった。外部から、そこへ一本の道(同上)があった。
この空地部分で、壮大な祭りの儀式がとり行われた。各地から集まった群衆は、司祭者たちのとり行う、この壮麗な儀式を見守っていたのであろう。諸磯(もろいそ)式土器の時代だ。このとき、八ヶ岳は“燃えて”いたのであろうか。
このような、古代信州の祭祀伝統とその様式、それが「ストーン・サークル」形式の大町上原遺跡を経つつ、やがて千居遺跡へとうけ継がれる。
わたしのいる学校(昭和薬科大学)が、この四月(平成二年)から移転する町田校舎、その“近く”の田端(たばた)遺跡も、“富士山の方角の見える配石遺構”だ。関東に「富士信仰」がひろがったのは、ただ室町や江戸時代の「富士見講」のせいだけではない。すぐれて縄文時代、その信仰が拡がっていった。そして東北地方南部、そしてさらに東北地方北部、あの大湯のストーン・サークルヘと辿り着いたのである。最近見出された、青森市の配石遺構、小牧野遺跡は、縄文時代後期前葉か、という。現在発掘進行中。やはり「配石遺構」と、その一部である「ストーン・サークル」形式は、“信州から北進した”のだった。
縄文という時代、それが海上では、「一大航海時代」ともいうべき活躍期だったこと、すでに説いた(第三章)。しかし、その活躍は、当然ながら「海上」だけではなかった。「陸上」でもまた、駸々(しんしん)と、その文化活動・生活形態、祭祀様式は“伝播”し、“受容”され、新しい文明を見事に花開かせて、止(や)む日とてなかったのであった。
『東日流外三郡誌』序論 日本を愛する者に 古田武彦 『新・古代学』第七集
『真実の東北王朝』目次へ